目次
PR
「毎日毎日、癇癪ばっかりでもう疲れた…。」
癇癪の対応は、パパママの悩みの一つだと思います。
特に幼児さんは、自分の気持ちを言葉で上手く表すことができないので、癇癪を起すことが多いでしょう。
そして、癇癪を繰り返していく中で少しずつ自分の気持ちと向き合い、切り替えができるようになるのです。
中には「癇癪がある=発達障がい」と思う方もいますが、100%そうとは限りません。
癇癪は子どもが成長していくうえで、必ずと言っていいほど通る道なのです。
しかし、子どもによくあることだとわかっていても、対応に困ってしまいますよね。
そこで今回は、保育士がおすすめする癇癪対策グッズをご紹介します😊💕
癇癪の時に避けたい対応!
まずは癇癪の時に気をつけたい、NG行動を見ていきましょう。
癇癪の時のNG行動4選
- こちらも感情的になる
- 落ち着いていないのに厳しく叱る
- おもちゃやお菓子で落ち着かせてそのままにする
- 危険な場所(屋外など)でそのままにする
毎日のように癇癪を起されていると、丁寧に対応できない時がありますよね。
しかし、子育てや子どもの対応に完璧や正解はありません。
上手くいかないことに落ち込まず、気をつけたいポイントを一つずつ確認しましょう。
こちらも感情的になる
ママやパパも忙しいなか、一生懸命に子育てをしています。
精神的に余裕がなくなってくると、ついカッとなってしまうときがあるでしょう。
しかし、癇癪を起している子どもに感情をぶつけても、もっと興奮させるだけになってしまいます。
グッとこらえて、冷静に対応しましょう。
周囲の安全が確保されているなら、飲み物を飲んだりトイレに行ったりして一度落ち着くこともおすすめです。
落ち着いていないのに厳しく叱る
子どもが癇癪を起している時に、物に当たったり人を叩いたりする時がありますよね。
そういう時は、つい厳しく叱ってしまいがちです。
しかし、癇癪を起しているときは、冷静ではないので人の話がしっかり聞けません。
子どもにダメなことを伝える時は、まず子どもを落ち着かせてからにしましょう。
おもちゃやお菓子で落ち着かせてそのままにする
子どもを泣き止ませるために、おもちゃやお菓子で対応することもあるでしょう。
その時にただ与えて終わりにしてしまうと、ご褒美になってしまいます。
与えた後に、「怒らないで優しく教えてね」と伝えることで子どもの認識も変わっていきます。
しかし、幼児さんが自分の気持ちを言語化するのには時間がかかるので、長い目で見ていきましょう。
危険な場所で放置する
大人も人間なので、子どもに癇癪を越されるとイライラしてしまいますよね。
自分もイライラしてきたら、一旦離れてクールダウンするのもおすすめです。
しかし、屋外や椅子の上などケガをする可能性がある環境の時は、離れてはいけません。
例えば、出先で癇癪を起された時は、人が少ないところに移動して落ち着かせましょう。

正解はないので、参考までに見てみて下さいね😊
癇癪の時に意識したいこと
前の項目で、癇癪の時に気をつけたいポイントをまとめました。
ここでは、意識しておきたいことをご紹介します✨
癇癪の時に意識したいポイント3つ
- まずは話を聞いてあげて、子どもを落ち着かせる
- 可能であれば代替え案か折衷案を提案する
- 今後どうしてほしいのか伝える
まずは話を聞いてあげて、子どもを落ち着かせる
子どもが泣き叫んで「〇〇してほしい!!!」と言って来たとします。
こういう時ってつい「それは今できません」と伝えてしまいますよね。
ここで一度、最後まで話を聞いて「〇〇してほしかったんだよね。ママもわかるよ、教えてくれてありがとう」など、安心させてあげる言葉を言ってあげましょう。
実際に願いを叶えられなくても、気持ちを受け取ってあげたという事実が大切です。
可能であれば代替え案か折衷案を提案する
例えば、子どもが明け方の5時に目を覚まして、「お外で遊びたい」と駄々をこねたとします。
本来であればもう一度寝直してほしいところですよね!
しかし、ここで「まだ暗いのでダメです。ねんねしてね!」と伝えると余計に子どもは泣き始めます。
そこで、「お外じゃなくて一緒に絵本見てみようよ(代替え案)」や「お日様が上まで出てきたら遊びに行こう(折衷案)」と伝えてみましょう。
今後はどうしてほしいのか伝える
子どもが自分の気持ちを伝えようとするのは良いことです!
ただ、泣き叫んだり物に当たったりされるのは困りますよね。
そこで、正しいコミュニケーションの仕方を伝えてあげましょう!
具体的には、「次からは怒らないで優しく教えてね」と伝えてみるのがおすすめです🌟

後は自分の気持ちを丁寧に伝える方法をレクチャーしよう✨
ただ、すぐにできることではないから、長い目で見てあげてね!
癇癪の時におすすめのグッズ
子どもは、言葉だけの情報だと意味が理解できないこともあります。
そんな時は、おもちゃを出して「これで遊んで落ち着こうか?」と、声をかけてみるのも手段の一つです。
ここでは、癇癪の時におすすめのグッズをご紹介します。
トンネル
|
|
【解説】
癇癪を起しているときは、まず落ち着かせるのがポイントです。
大人も感情的になっているときは、一人になった方が切り替えやすいのではないでしょうか。
それは、子どもも同じです!
しかし、小さい子を一人にしておくのは心配ですよね…。
そこで、この不透明なトンネルが役に立ちます✨
トンネルの中=自分だけの空間となり、リラックス効果が期待されるのです!

あくまでも子どもが進んで入ったら、そっとして落ち着くまで待とう!
遊び始めて自然と気持ちを切り替えられる子もいるよ😊
また、夏場はトンネルの中が籠るので、熱中症にも注意してね!
おもちゃのテント
|
|
【解説】
先ほど紹介した、トンネルと同様に自分だけの落ち着ける空間として使えます!
子どもが癇癪を起してて、抱っこしても話しかけても落ち着いてくれない時はさっとテントを出してみましょう。
自分から中に入ってくれたら、そのまま静かに様子を見守るのがおすすめです🏠
もしかしたら、一人になりたい気持ちだったのかもしれませんね。
落ち着いたころに話しかけてみて、気持ちを切り替えてあげましょう。

もう少し大きな子どもだったら自分の部屋で落ち着けるけど、幼児さんだと一人にするのは心配だよね💦
そんなときは、このテントがおすすめ💖
オルゴール
|
|
【解説】
落ち着いているメロディを聞くと、大人もリラックスできますよね。
オルゴールには、子どもの心を穏やかにする効果もあると言われています。
そして、このオルゴールにはシアターもついているので、夜間の癇癪対応にもおすすめです♬
見た目も可愛らしくて、子どもの心を掴んでくれるのではないでしょうか🐧💖

汚れても綺麗にできるので、長く使えて嬉しいですね😊
スクイーズ
|
|
【解説】
子どもは耳だけではなく、手からの感覚からも情報を得ています。
このスクイーズ独特の感触は、リラックス効果やストレス解消があるのでおすすめです🍇🍌🍎
また、一般的にスクイーズで遊ぶのは5歳からとされています!
破片や内容物を誤飲してしまうと、命の危険があるので口に物を入れる癖がある子どもには出さないでください。
どの玩具でもそうですが、遊ぶ際にはそばから離れずに見守ってあげることをおすすめします!
そして、対象年齢が記載されているものは、その通りに使用してくださいね😊

冷たくて柔らかい独特の感覚がクセになる!
他にも子どもの手の感覚や、動作を刺激する玩具でもある🍇
感情が題材になっている絵本
|
|
【解説】
気持ちをコントロールするために、まずは自分の「怒り」や「悲しみ」といった感情に触れられるようにしましょう。
そして、言葉で説明するよりも絵本を使ってイラストから伝えた方が子どもは理解しやすいです!
この絵本は、合わせて気持ちのコントロールの仕方を、具体的に教えてくれます。
子どもだけではなく、大人も読んでいると参考になることが多い絵本です😊

「感情」という本来は目に見えないものを、イラストで表現することで子どもにも伝わりやすい✨
グッズを出すときに気をつけたいこと

先述したように、グッズを出すことが癇癪に対するご褒美にならないようにしましょう。
グッズを使用するのは、あくまでも心を落ち着かせるための手助けです。
そして、適切な感情の出し方を、繰り返し子どもに伝えていきましょう。
1歳~2歳であれば、自分の気持ちを落ち着いて言葉にするのは難しいので、「落ち着く経験」がゴールでもいいのかなと感じます。
年齢としては3歳以上を目安に、怒ったり泣いたりせず言葉で伝えられるよう一緒に練習していきましょう✨
まとめ
PR
今回は、癇癪の対応についてまとめました。
子育てには正解がなく、また子どもによっても関わり方が変わってきます。
記事の中で紹介していることはあくまでも一例で、絶対ではありません。
「こういうやり方もあるんだなぁ」と思っていただけたら幸いです!
癇癪の対応に困っている方は抱え込まず、ぜひ園の先生や地域の子育て支援施設に相談してみて下さいね😊
この記事が、癇癪で悩んでいる方の参考になれば嬉しいです🌟
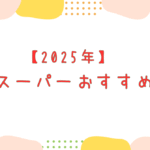
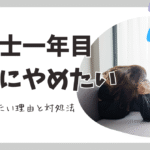
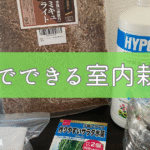
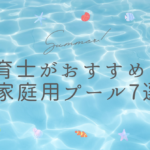
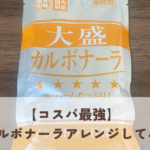
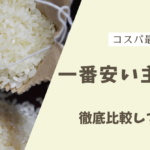
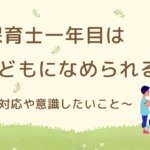

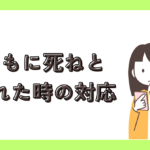


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3eccf2f3.79ffb8de.3eccf2f4.fca8d83f/?me_id=1400568&item_id=10001761&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fasaito1210%2Fcabinet%2F08620581%2F09091653%2F43.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ecd06d8.b8e80d69.3ecd06d9.40e076dd/?me_id=1375897&item_id=10000841&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Froomnhome%2Fcabinet%2F09409666%2F09728980%2Fimgrc0114268665.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ecd1560.ef49945d.3ecd1561.c7715e36/?me_id=1394398&item_id=10000024&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Frobotplaza%2Fcabinet%2Fsleep-toy-penguin%2Fpenguin-child3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3ecd2036.af2065d5.3ecd2037.bbcfd682/?me_id=1295522&item_id=10001695&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frainbowbridge%2Fcabinet%2Fclass%2Fnew_class%2Fsat-236-zt-.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3af9e6e5.a8863fc2.3af9e6e6.68984569/?me_id=1213310&item_id=20068983&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2724%2F9784790272724.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

